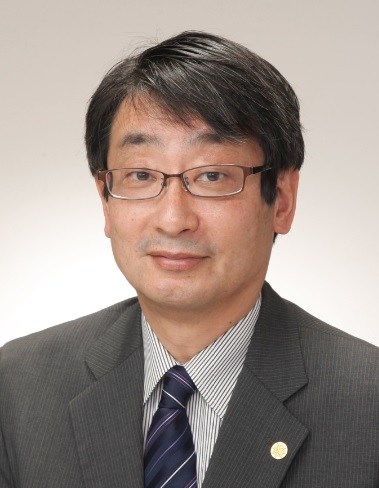【事業承継の基本】6.従業員承継の進め方(後継者視点)

従業員として勤務してきた方が、現経営者から後継の指名を受けて経営を行う立場になることは、大きなやりがいを感じられるものと思います。それまでの事業への貢献が認められた証でもあります。また自らがビジネスをリードする人生をおくりたいと考えていた人にとっては、一から事業を始めるよりはるかに有利なスタートができるものとなります。一般的な事業承継での後継者が受けるメリットは「【事業承継の基本】1.事業承継のメリット―後継者視点」で記載していますが、特に従業員として承継する場合は一般的に以下の優位性があります。
・業務の現場を熟知しており、知識やノウハウの移転への障壁は少ない。
・取引先・従業員など関係者の理解が得やすい
一方で、以下が課題になります。
・株式・事業用資産の移転にかかる費用負担が大きい
従業員は十分な資金力がないケースが多く、課題になります。最近はエンプロイー・バイアウト(EBO)などのスキームも多く使われるようになってきました。EBOは従業員が別会社を作り、この会社に金融機関から借り入れを行い、株式を現経営者から買収する方法です。後継者側としては買収した会社が収益を上げた場合は(その利益の使い道(利益処分)は株主総会の決議できめられますので)後継者の立ち上げた会社に配当金などで還元し、借入金の返済に充てることができます。そのうえで後継者が次の後継者に株式を売る場合、さらなるお金を手にする可能性もでてきます。
・会社に借入金がある場合の個人保証対応
また、会社に借入金がある場合は、経営者となる後継者の個人保証が求められるケースが多くあります。これについては近年「経営者保証ガイドライン」の利用が浸透してきています。
(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/)
これは中小企業庁と金融庁より示されているもので「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」とされ法的な拘束力はありませんが、一定の条件を満たせば経営者保証を解除する道も開けてきています。
以下に従業員承継に関する後継者側の進め方を記述します。
【後継者側の進め方】
1.後継者の候補として現経営者から指名を受ける
後継者の指名をうける時点が事業承継の始まりになります。既に継続している事業を行う会社を承継できることは大きなアドバンテージがあります。自らの従業員としての会社への貢献や、将来の事業展開や従業員を任せてよいという現経営者の信頼が背景に必要になります。日頃から以下をおこなうようにすることが有効になってきます。
・会社の理念やビジョンを理解した行動を行う
・社内でのリーダーシップを発揮する
・経営実施に向けた知識吸収を行う
2.事業の見える化を現経営者と共に行う
事業内容や関係先、財務状況、人事状況など経営に関しては現経営者が基本的には把握していますが、視点の違う従業員後継者も自分の考えで現在の事業内容や強み・弱み・機会・脅威などを整理することは重要になります。現経営者と後継者が「事業承継の見える化」を一緒になって行うことが事業承継の第一歩になります。
3.事業承継後のビジョンを明確にする
まず、事業承継後のビジョンを明確にすることが重要です。その時々の社会環境や顧客ニーズは変わっています。従業員への承継とはいえ、単なる世代交代ではなく企業の成長と存続を見据えた計画が求められます。最終的に事業承継後のビジョンを実現するのは後継者になります。この際に現経営者の考えを踏まえることで社内外の関係者の理解を得やすくなります。また後継者が複数となるケースもあります。この際は役割決めを行って進めます。
4.不足している業務の経験を積む
業務経験の提供や研修を通じて、必要なスキルと知識を習得します。従業員は一定の業務経験を積んでいるケースが多いですが、営業・購買・会計・人事など経営を行うに当たって不足する業務のキャリアを積んだうえで、経営者の片腕として経営者自身からその知見を体験し学ぶことをお勧めします。
5.経営者と必要な知識習得
経営管理や生産管理、販売管理、会計、人事、コミュニケーション、IT、WEBなどは会社内で基礎知識を得られない場合も多く、研修を受けることをお勧めします。中小企業大学校などが行っている「後継者塾」などを受けるのも一つの方法です。当社ではより身近な題材で学ぶことにより、知識を得やすくするため「自社を題材にした個別後継者教育」も行っています。
6.親族への説明
従業員から経営者に立場が変わることで自らの責任は重くなります。場合によっては個人保証などを背負うケースもでてきます。親族が協力できる環境を作るために親族への説明を行うことをお勧めします。後継者として新しい人生を踏み出すことの明示となります。
7.株式、会社及び個人資産の移転を受ける
株式や会社の事業用資産を贈与や相続、売買を通じた移転を受けます。基本的に移転をリードするのは現経営者となりますが、近年ではEBOなどを使用する例も多くなっています。
8.現経営者とともにステークホルダーへの説明
社員、取引先、金融機関などに事業をつなぐことを示し、事業承継後のビジョンを説明
します。これにより事業継続による信頼を確保し、引き続きの協力依頼を行います。
9.承継後の事業開始
新しいビジョンによって後継者がリーダーシップを持って事業を開始します。必要に応じて現経営者のサポートを得て、円滑に経営に進められるようにします。
従業員から経営を行う立場になる機会を得ることは大きな人生のチャンスになると思います。一方、その責任は大きくなります。ご家族に理解してもらい協力を得ることも併せて進めましょう。