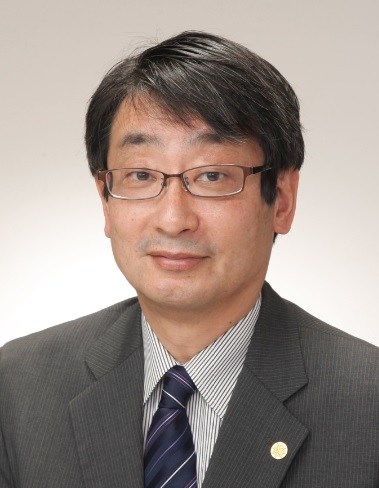【事業承継の基本】5.従業員承継の進め方(現経営者視点)

2024年の帝国データバンク調査によると、経営者の事業承継は内部昇格(従業員承継)が第一の選択肢になりました。背景には親族間承継の減少もありますが、従業員への事業承継には一般的に以下のメリットがあり、とても堅実な方法と考えられます。
・業務の現場を熟知しており、知識やノウハウの移転に関する負荷は低い。
・取引先や顧客など関係者の理解が得やすい
・親族内での調整などの負荷は低く、事業に特化した承継としやすい。
一方で、以下が課題になります。
・株式・事業用資産の移転にかかる費用負担が大きい
従業員は十分な資金力がないケースが多いです。また相続・贈与を使った移転は経営者の親族の法的な権利や心情を考えると使いずらくなります。
この対応としてエンプロイー・バイアウト(EBO)などのスキームも多く使われるようになってきました。EBOは従業員が別会社を作り、この会社に金融機関から借り入れを行い、株式を現経営者から買収する方法です。ホールディング方式とも呼ばれます。現経営者は株式を売ったお金を手にすることができますし、そのお金はいずれ親族への贈与・相続の原資にもなります。また後継者側としては買収した会社が収益を上げた場合は(その利益の使い道(利益処分)は株主総会の決議できめられますので)後継者の立ち上げた会社に配当金などで還元し、借入金の返済に充てることができます。そのうえで後継者が次の後継者に株式を売る場合、さらなるお金を手にする可能性もでてきます。
以下に従業員承継に関する現経営者側の進め方を記述します。
【現経営者側の進め方】
1.事業を「見える化」する
事業内容や関係先、財務状況、人事状況など経営に関する内容など事業承継をめぐる状況を整理し「見える化」します。従業員承継の場合は既に知っている分野もあり、後継者と一緒に進めることをお勧めします。
2.事業承継計画を策定
「見える化」した内容を踏まえ、事業承継の方針を整理します。方針に従い実施内容を洗い出し、年ごとの粒度でスケジュールを策定します。後継者の選定が必要な場合はそのプロセスを含む計画を作成し、関係者間で共有します。
3.後継者の候補抽出と選定、調整
個人の適性や能力、将来の考え方を考慮し後継者候補を抽出します。そのうえで後継者と調整をおこないます。特に従業員承継では従業員本人の理解だけでなくご家族の理解が得られずにかなわないケースもありますので、そのケアやフォローも検討します。
4.後継者育成(業務経験)
業務経験の提供や研修を通じて、後継者に必要なスキルと知識を習得させます。従業員の場合、一定の業務経験は持っておりその経験は生かせますが、経営全般を見られるよう未経験の分野でのキャリアを積んだうえで、経営者の片腕として経営者自身からその知見を体験し学ぶことをお勧めします。
5.後継者育成(研修)
経営管理や生産管理、販売管理、会計、人事、コミュニケーション、IT、WEBなどは従業員としては基礎知識を得られない場合も多く、研修を受けることをお勧めします。中小企業大学校などが行っている「後継者塾」などを受けるのも一つの方法です。当社ではより身近な題材で学ぶことにより、知識を得やすくするため「自社を題材にした個別後継者教育」も行っています。
6.株式、事業用資産の整理と移転計画
株式や会社の資産・負債を整理し、従業員承継では基本的には売買を通じた円滑な移転方法を計画します。円満な事業承継を実現するためには現経営者の親族が協力できる環境を作ることも必要になります。また資金力の乏しい従業員への移動を円滑にするため戦術のEBOのスキームを使用する例も多くなっています。この実施においては金融機関の協力が不可欠になります。
7.現経営者親族への説明
従業員への承継であっても、親族が協力できる環境を作るためには親族への説明を行うことをお勧めします。経営者としての引退と新しい人生を踏み出すことの明示となります。
8.ステークホルダーへの説明
後継者とともに社員、取引先、金融機関などに承継計画を説明します。後継者となる従業員以外に幹部などがいる場合はそのケアも行います。役割を明確にして重要な権限と責任を付与するなど丁寧な処遇を行いましょう。これにより事業継続による信頼を確保し、引き続きの協力依頼を行います。
9.経営権移譲の実施
株式や事業用資産の移転や登記上の変更、許認可の変更など手続きを進めます。法的な移譲準備を進めます。
10.アフターリタイヤメントの計画
「経営の重荷に耐えて、頑張ってこられた経営者にとって事業承継はその肩の荷を降ろすものとなります。それは「新しい人生」へ向かうための区切りをつけるものとなります。」(事業承継協会の資料より)
アフターリタイヤメントの計画としては、以下のような実施例があります。
・後継者や会社への記録
自ら経営を行ってきた思いを書き留めることは、後継者への引き継ぎの記録となり、会社案内にもなります。
・資産の適切な管理と投資戦略の構築と退職生活の予算と支出計画
・定期的な健康チェックと運動習慣の確立、バランスの取れた食事と栄養補給
・趣味や新しい挑戦の追求
引退した後には経営者の「新しい人生」が始まります。この中での充実した計画を立てていくことをお勧めします。
従業員承継は、現経営者の行ってきた事業を再現することにおいて最も堅実で実践的な方法と
も言えます。事業承継に係る時間や負担も小さいと考えられます。現経営者としても有望と思える従業員がいる場合は、早めに本人の意思など確認し準備を進めることをお勧めします。