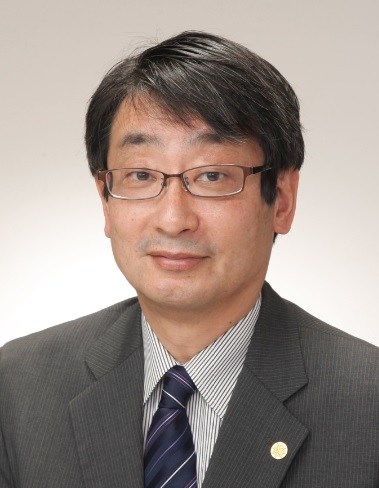【事業承継の基本】2.事業承継のメリット―現経営者視点

2024年は事業承継において大きな転機になりました。長らく承継先としてトップであった同族承継に代わって、内部昇格が一番の選択肢となったのです。またM&Aも急成長しています。
※帝国データバンク「全国「後継者不在率」動向調査(2024年)」「代表者・就任経緯別推移」を参照
https://www.tdb.co.jp/report/economic/succession2024/
この状況を帝国データバンクでは「脱ファミリー化」が加速していると表現しています。
この背景としては親子間の関係の変化や少子高齢化社会などがありますが、その他にも環境として資金力が弱い従業員が資金を調達できるスキームであるエンプロイーバイアウト(EBO)の普及や経営者保証ガイドラインの広まり、M&Aプラットフォームなどの普及により小規模の事業者でも企業の売買ができる仕組みが整備されつつあることも見逃せません。
かつては高齢化して子供がいなければ廃業と考えていたであろう企業も、事業を後生に残せる可能性が増えています。
現経営者が事業承継を通じて事業を譲渡することは、後継者はもちろん関係者や社会に多くのメリットをもたらします。これにより相応の対価を得られる可能性もでてきます。
【現経営者にとってのメリット】
1. 行ってきた事業が継続される
事業承継により、これまで培ってきた事業が継続されることで、顧客基盤やブランド価値を守り、信頼を維持することが可能です。特に地域や業界に深く根付いた企業であれば、その影響力を絶やさずに存続させることができます。
2. 従業員雇用が継続される可能性が高い
経営が後継者に引き継がれることで、従業員の雇用が守られやすく、長期的な働き場所の提供が可能となります。突然の経営停止や清算を防ぐことで、従業員の生活基盤を守り、会社への信頼感を維持できます。
3. 会社の負っていた社会的な責任が保てる
会社が地域社会や業界内で果たしてきた役割や貢献(例:雇用創出、地域経済の活性化、社会貢献活動など)を引き続き担うことが可能です。事業承継により、企業が果たすべき社会的責任が中断されずに続きます。
4. 個人としての資金獲得のメリット
事業承継では経営者個人にとっても資金面でのメリットがあります。以下に、親族への承継、従業員への承継、M&Aによる承継それぞれの特徴を示します。
(1) 親族への承継
経営権を家族内で引き継ぐことで、事業の一貫性を確保しやすく、贈与や相続時の税制優遇措置(事業承継税制の利用)が得られる場合があります。退職金を使って株価を下げて親族への株式移動を容易にするとともに、現経営者の老後など資金確保をするケースも多いです。親族の財産形成にも寄与できます。
最近は親族間でも遺留分対応など相続に関する面倒な対応回避や現経営者の資金確保目的から、親族間であっても別会社を後継者が作って、その会社に株式を売り渡すスキーム「MBO」も普及してきています。
(2) 従業員への承継
会社の内情を理解している従業員が引き継ぐことで、スムーズな事業運営が期待できます。雇用の維持が可能で、社員のモチベーション向上にもつながります。
こちらも退職金を使って株価を下げて親族への株式移動を容易にするとともに、現経営者への老後対応など資金確保をするケースも多いです。資金力が弱い従業員が資金を調達できるスキーム「EBO」も普及してきています。
(3) M&Aによる承継
他企業や投資家への売却により、大きな資金を一度に得ることも可能です。買収企業が持つノウハウやリソースを活用し、さらなる事業成長が期待できます。基本的にM&A後は譲渡先が経営判断をすることになります。会社の文化や方針が大きく変わる可能性があるため、売却時に条件など調整が重要です。
上記にメリットを記載しましたが、すべての企業経営者がメリットを享受できるわけではありません。「1.事業承継のメリット―後継者視点」で記載したメリットがでないと買収側が判断した場合は譲渡が難しくなります。主なポイントとしては以下があります。
a. 買い手にとって魅力のある企業であること
魅力的な事業内容、安定した収益、健全な財務状況を備えた企業は買い手にとって価値が高まります。知名度やブランド価値、優れた従業員、独自の技術・ノウハウがあることなども強みとなります。
b.後継者が再現できる状況での譲渡であること
会社の活性がさがってしまい、顧客や従業員が離れてしまう、技術が陳腐化しているなどしていれば後継者が事業を再現することは難しくなります。また現経営者による属人化した業務も事業を再現することは難しくなります。まずは経営を見える化し、会社とご自身にとって適したタイミングを見極めることが必要になります。